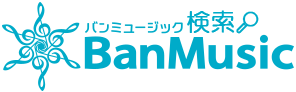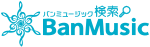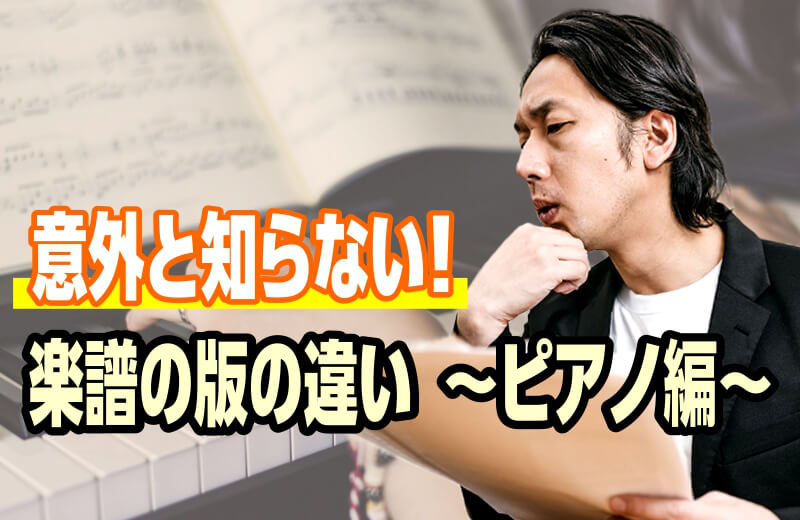
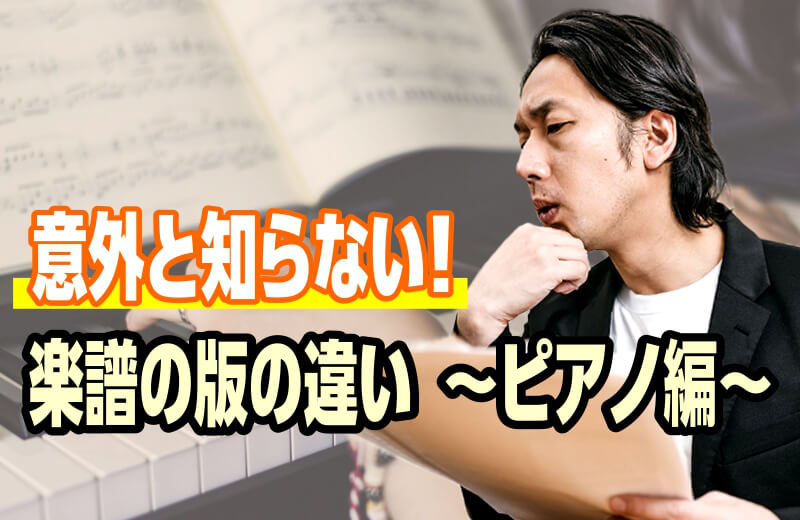
意外と知らない!楽譜の版の違い~ピアノ編~
新しい楽譜を購入するとき、「〇〇版で」と先生から指定された記憶はありませんか?
同じ曲を様々な出版社が販売しており、何が違うのかよくわからないまま購入している方も多いと思います。
今回は出版社の特徴をご紹介します。
楽譜の出版社はどんな種類があるの?
楽譜は
- 原典版
- 校訂版
の2種類があります。
この2種類について少しだけご説明します。
原典版
その名の通り作曲者の書いた譜面をそのまま再現したものです。
とはいっても、作曲家が書いた自筆の楽譜をそっくりそのまま出版しているのではありません。
作曲家の初版や書き込みを見て作曲家の意図を汲んで作成されます。作曲家自身が頻繁に改定したりしている場合もあり、原典版を作成するのは大変な作業です。
作曲家の意図を自分で汲む力をつけるために、まず原典版で譜読みするということはピアノを勉強する上で必須と言えます。
校訂版
演奏家や専門家によって書き換えられたものが校訂版です。
もちろん音符を書き換えることはありませんがフレーズや運指、ペダル、強弱を演奏者が演奏しやすいように、また演奏効果を高めるために作成されています。
日本の出版社から出ている校訂版は日本人の手の大きさに合うような運指であることが多く、参考にしやすいです。
 それぞれの出版社の特徴は?
それぞれの出版社の特徴は?
それでは早速どんな出版社が楽譜を出しているのか、どんな特徴があるのか、有名な出版社を厳選してご紹介します!
春秋社版
春秋社は日本の出版社です。カバーのついている楽譜で、手にしたことのある方も多いのではないでしょうか。ピアニスト、ピアノ教育者として有名な井口基成さんによる校訂版です。
初心者にもわかりやすい、丁寧な楽曲解説がついています。
全音
この青い楽譜はピアノを弾いたことのない人でも見たことがあるのではないでしょうか。
グッズにもなっている日本人おなじみの全音出版社です。楽譜以外に、音楽関連の書籍も豊富です。
この全音楽譜も校訂版です。
全音はなんといっても安価なことがうれしいポイントです。
ピアノピースの種類も豊富で、1曲だけやりたいのに全集を買わなければならないなんてこともありません。
とりあえず購入できる気軽さはナンバーワンですが、ピアノを勉強するための楽譜と考えると少し物足りなさがあるかもしれません。
ウィーン原典版
真っ赤な楽譜で目を引くのが音楽之友社から出版されているウィーン原典版です。
音楽之友社の出版なのになんでウィーン原典版なの?と疑問に思われましたか?
ウィーン原典版はウィーンに拠点を置いている「ユニバーサル・エディション」という出版社と音楽之友社が提携しているのです。
作曲家の残した様々なものや徹底的に比較して制作されています。そしてアシュケナージ、ブレンデルといった超一流のピアニストたちが校訂に関わっていることもあり世界的な評価がとても高い楽譜です!
ヘンレ版
ちょっと地味な表紙のヘンレ版。こちらは「ギュンター・ヘンレ」というピアニストによって設立されたドイツの楽譜です。
ヘンレ版は「THE原典版」と呼びたくなるほど、とにかく情報量の少ない楽譜です
運指やペダリングなど、ほかの版に比べて圧倒的に何も書かれていません。作曲家の意思を自分でしっかり解釈したい人には向いています。
また、このヘンレ版の大きな特徴が「紙がもろい」ということです。
ヘンレ版専用のカバーまで販売されているほどすぐにぼろぼろになります!
値段が高いのにこんなか紙質?と言いたくなるレベルですが、
- 照明で紙が反射しない
- 鉛筆での書き込みがなめらか
というメリットがあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
同じ曲なのに、版によってかなり違いがあるなんて、なかなか奥が深い楽譜の世界です。
ご自分の勉強スタイルによって選べば音楽の世界が広がること間違いなしです。
じっくり吟味して納得の版を見つけてくださいね。