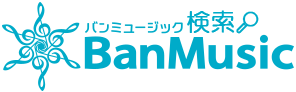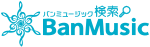フルート正しいピッチで吹こう!後編・普段の練習法
「正しいピッチで吹きたい! 前編・チューナーの使い方」では、「チューニングしたのに、演奏したらピッチが違う」という問題を解決するため、まずはチューナーの使い方をおさらいしました。
今回は、「ちゃんとチューニングしたのに、演奏するとやっぱりピッチが違う」という人のために、その理由と普段からの練習方法を解説していきます!
演奏を楽器に任せてはダメ!
音ごとに吹き方がある
チューナーをしっかりと使い、基となる音を上手に合わせられました。「でも演奏するとやっぱり他の楽器と合わない!」ということも、初心者のうちはけっこうあるのです。安心してください! 穿いてますよ
その理由はズバリ、あなたがただ音を出している状態だからです。正しい指使いで息を吹き込めば、正しいピッチで鳴るのではないのです。どんなに良いフルートを買ったとしても、自分が何もせず音階全て正しい音程で鳴ってくれるということは、絶対にありません。
歌うときは、音の高さを自分で取りますよね。フルートだって、それぞれの音の高さに合った息を自分で覚えて、それぞれ吹き分けないといけないのです。押せば正しいピッチで鳴ってくれるピアノとは違い、フルートは息の速さ、強さ、構える角度などで、簡単にピッチが変わってきます。
歌って練習!
それぞれの音にそれぞれの吹き方がある、と分かりました。吹き方と言っても、口の形や構え方を変えるなど、大きな動きをしてはいけません。主に、息のスピードを変えて行きます。音によっては口の中の意識するポイントを変更することも必要ですが、これは楽器や人それぞれの口の形などによっても違いますので、先生に指導を受けるチャンスがあれば訊いてみてください。
それよりもまず、やらなければいけないのは、正しい音の高さを自分が覚えることです。声を出して歌うと良いでしょう。自分が練習している曲の、ゆっくりとした動きのところからやってみてください。
正しい音程が頭に浮かぶでしょうか?
次の音へ切り替わったとき、不安定な音程になっていませんか?
チューナー再び登場
ここでチューナーを使いましょう。
自分で歌った音程が、ちゃんと合っているかチェックします。かなり神経を遣うことと思います。
でも、これが大事なのです。音を合わそうと慎重になっている時、すごく身体を使っていませんか? 身体の中を意識してみてください。合わせようと、おなかをはじめ、全身で音程を取ろうとするのではないかと思います。
フルートを吹くときも、これくらいの慎重さで音を出しましょう。
フルートを吹いてみましょう
先ほど歌ったものを同じフレーズを、今度はフルートで実際に吹いてみましょう。最初はゆっくりでOKです。音を出すときに、その音の高さを想像して、同じピッチで出せるように慎重に吹きます。高い音になれば、身体が頑張って音程を取ろうとすると思います。その変化が大事なのです。
音程を取る練習も日課に!
ロングトーンとスケールを有効に使う
プロのフルート奏者は、どんなに速いフレーズでも、それぞれの音の吹き方を瞬時に変えて吹いています。楽器を持たずに歌わせてみても、コンマ数秒単位で息をコントロールできているのでそこそこ正しく歌えます。
ドレドミドファ、ドソドラドシ……と、1秒に6つずつ歌っても音程が取れます。
頭の中に正しい音程を鳴らし、その高さに相応しい息を出していくには、練習が必要です。ロングトーンはしていますか? 次の音を出す前に音の高さを想像して身体を使って音を出します。また、スケールの練習の時も、ひとつひとつの音を意識して、身体を変化させながら吹いていきます。
ロングトーンやスケールは、ただ音を出すだけ、ただ指を動かすだけの練習にすると、もったいないです。基礎練習の時間をしっかり活用しましょう!