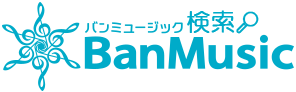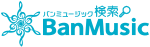ピアノが日本に伝来したのはいつ?シーボルトとの関係って?
今回のコラムでは、日本にピアノがいつ伝来したのか、その歴史について紐解いてみましょう。日本にピアノが伝わったのは、江戸時代、鎖国下であったといわれています。オランダ陸軍医であったドイツ人のフィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルトによって持ち込まれたピアノ。どのようなものだったのでしょうか?
日本に現存する最古のピアノ

シーボルトが1823年に日本に持ち込んだピアノは、1819年製造の、スクエアピアノというピアノでした。スクエアピアノは、安価ということもあって当時イギリスで人気がありました。200年以上前に作られたピアノですが、なんと現在も美術館に展示されており、私たちも見ることができます。2009年に修復された際、演奏できるようになり、コンサートも開かれています。山口県の熊谷美術館(くまやびじゅつかん)にありますので、興味のある方は見に行ってみてくださいね。
スクエアピアノとは?ピアノの歴史

ピアノという楽器自体が発明されたのは、1700年頃のイタリアでした。「弱音と強音を出し分けられるチェンバロ」という意味の「Clavicembalo col piano e forte(クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ)」というのがピアノの正式名称で、当時主流だったチェンバロという楽器を基にして作られました。チェンバロは弦を弾いて音を出すので強弱がつけられませんでしたが、ピアノはハンマーで弦を叩いて音を出すので強弱がつけられるというわけです。
時代は下って、1760年頃から、スクエアピアノが登場します。重厚な書斎用机のような美しいデザインをしたスクエアピアノは、19世紀中頃にアップライトピアノにとってかわられるまで家庭用ピアノとしての地位を占めていました。長方形のケースの中には、ハンマー上部に弦が斜めに張られています。初期のスクエアピアノは、現代のピアノに比べて音量が小さく、連打や音を伸ばすことが難しいなど、発展途上の部分もありました。さらに、ハンマーが弦を打った後すぐに離れないものもあり、弾きこなすには独特のコツが必要でした。しかし、その音色は非常に柔らかく、1860年代には金属フレームが導入され、弦の張力を高めてより大きな音量を得ることも可能になりました。
シーボルトと熊谷五右衛⾨義⽐

長州藩御用商人・熊谷(くまや)家の4代目、五右衛⾨義⽐(ごえもんよしかず)はシーボルトと交流があり、 シーボルトが開いた鳴滝塾の⾨下⽣を⽀えました。シーボルトが1823年に持ち込んだ愛用のピアノは、帰国の際に、熊谷五右衛⾨義⽐に贈られました。ピアノには、「我が友クマヤへ」とオランダ語でサインが書かれています。
まとめ
今回のコラムでは、江戸時代にドイツ人医師シーボルトが日本に持ち込んだスクエアピアノの歴史を紹介しました。このピアノは日本最古として現存し、山口県の熊谷美術館で見学できます。チェンバロとは異なり強弱がつけられるピアノの変遷、そしてシーボルトと熊谷五右衛門義比との交流についても解説しました。