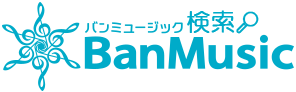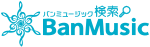楽器初心者必見!縁の下の力持ち、コントラバスの魅力を紹介!
コントラバスはじめるきっかけとなるのは部活動やサークルだったりと様々です。見た目のインパクトは大きいですが、普段あまりメロディを担当することもなく、ちょっと地味な印象。なのでコントラバスを第一希望とする人は多くなく、どちらかというと「コントラバスを弾いてみない?」と言われてはじめる人が多い傾向にあります。部活動によってはパートに自分しかいなかったり、周りに教えてくれる人がいないという問題もありますが、正しい知識と奏法を身につけコントラバスの奏でる低い音の虜になる人もたくさんいます。これから部活動やサークルでコントラバスをはじめた人向けに、楽器の魅力や上達の秘訣をいくつかにわけてお伝えします。
コントラバスって?
コントラバスは、オーケストラの中で最も大きい弦楽器。舞台上手に並び、小さい編成の場合は1〜2本、大きな編成になると6本〜8本…いや、時には10本なんて巨大な弦楽器が並ぶのですが、その光景には圧倒されます。舞台の真ん中でオーケストラをまとめてくれる指揮者よりも、もしかしたら目立つかもしれない。音を出せば「ボー」っと地の底からなら響くような最低音を鳴らし、オーケストラでは「縁の下の力持ち」として他の奏者たちを支えています。
皆が注目するようなメロディを演奏する機会は少なく、主に伴奏を担当しているのですがコントラバス奏者の腕でオーケストラのレベルが決まると言われているほど重要なパートです。
コントラバスが活躍するジャンルと呼び名
コントラバスは、クラシック音楽をはじめとしたオーケストラ、吹奏楽で使用されるほか、ジャズやポップス、ロック、ロカビリー、カントリーなど様々なジャンルでも使用され、ダブルベース、ウッドベース、アップライトベース、ストリングベース、弦バスなど多くの呼び名を持つ楽器です。中でも、弦バスという呼び方は吹奏楽界だけの呼称となっています。
どのジャンルでも大切なのは基礎

「縁の下の力持ち」と呼ばれ多くのジャンルで活躍するコントラバス、どの楽器にも言えることですがコントラバスを手にした頃にいかにコツコツ取り組むかで上達の早さが変わってきます。
部活動やサークルでコントラバスをはじめた方の多くが自己流で弾き始めたという傾向が多く、基礎を見直してみると弾きやすさも音も劇的に変化することがあります。
もしパートに先輩がいなく自分1人しかいなかったり、周りに教えてくれる人がいないという方は、是非コントラバスの魅力を知り、基礎的な知識を身につけ、日々の練習に励んでください。
中でも
- 楽器の構え方
- 左手の形
- 右手の使い方
の3つのポイントを初心者のうちに覚えてくことが上達への近道です。
コントラバスの教則本にも必ず書かれている内容ですので、まずはこの3つを覚えていくと良いでしょう。
まとめ
今回は「縁の下の力持ち、コントラバスの魅力を紹介」と題した楽器の紹介と初心者の方がまず覚えておくとよい楽器の構え方や左手、右手の基礎を解説しました。次回は、コントラバスの演奏動画を紹介します。ここで解説した3つのポイントを動画を見ながらチェックしてみてください。