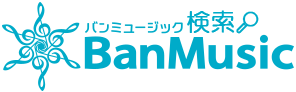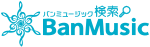ハーモニクスによるチューニングに挑戦!耳を鍛えるチューニング方法。
今回はハーモニクスを使ったチューニング方法について解説します。ハーモニクスは開放弦で弾いている音の1オクターヴ上を軽く触れることによって出すことのできる「倍音」のことをいいます。
このハーモニクスとポジションの横の関係を利用して各弦の音を合わせるチューニング方法がハーモニクスを使ったチューニングであり、実際にオーケストラでは練習前や開演後のチューニングでこの方法が用意られます。また、ハーモニクスの指定(記号)が出てきたり、第6ポジションから出てくる開放弦の1オクターヴ上の音(G,D,A,E)を弾く際にもハーモニクスを使って音程を確認することができるので覚えておくと良いでしょう。
使用するポジションは第3ポジション
ハーモニクスを使ったチューニングの方法で使用するのは第3ポジションです。
一度、各弦の第3ポジションの音を確認しておきましょう。
第3ポジション 各弦の音(コントラバス運指表参照)
-
- G線(ドード♯ーレ)
- D線(ソーソ♯ーラ)
- A線(レーミ♭ーミ)
- E線(ラーシ♭ーシ)
弦を押さえるのではなく軽く触れる(横に指を置く)
ハーモニクスの音を出すときは、第3ポジションの位置で弦を押さえるのではなく左手のフォームをキープしたまま軽く触れます。上手く触れられるとソプラノ歌手のような高くて綺麗な音が鳴ると思います。
少しでも触れる位置がずれてしまうと音が出ないので注意しましょう。
教則本では「弦に軽く触れる」
と書かれていることが多いですが、指をしっかりと固めて弦の真横(右側)に指を置き、弦に指を少し引っ掛けるようにするとしっかりとした音が出せます。
各弦で同じ音を出し音を合わせる
ここで大切なので横の関係です。まずはオーケストラのチューニングで基準となるA(ラ)の音を出してみましょう。実際にはオーボエのAの音からヴァイオリンがAを合わせ、全体がそのAに合わせます。
第3ポジションのD線の4の指を押さえるとA(ラ)の音が鳴るでしょう。その際に、押さえるのではなく弦に軽く触れて倍音を出します。そして左手のフォームはキープしたまま、A線の1の指で押さえる場所を軽く触れると同じ音が出せます。こうしてD線とA線をハーモニクスのA(ラ)の音で合わせていきます。
次に、第3ポジションで構えたままD線の1の指とG線の4の指の位置で鳴るD(レ)の音を使って、A線の4の指とE線の1の指の位置で鳴るE(ミ)の音を使って各弦を合わせていきます。
まとめ
ハーモニクスを使ったチューニングの方法、いかがでしたか?この方法は実際の合奏現場で使用するほか、演奏中に音が狂ってしなった場合もサッと合わせることができます。特に吹奏楽では管楽器が演奏中に音が高くなっていくことに対して弦楽器は弦が緩み音程が下がっていくのでこうしたチューニング方法を覚えれば、合奏中や休憩中にちょっと確認したいときにも便利です。
はじめはチューナーを使って合わせていって、慣れてきたらD線のA(ラ)の音だけチューナーで合わせ、他の弦は自分の耳を頼りに合わせていきましょう。
はじめは時間がかかるかもしれませんが、音程の高低差を聴き分ける訓練にもなるので大変おすすめです。