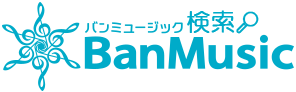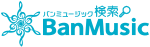コントラバスの右手の話。弓の持ち方とボウイング練習に挑戦!
これまでコントラバスの魅力を紹介、楽器の構え方を解説してきました。今回はいよいよ楽器の音を出してみましょう。コントラバスは右手で弓を持つ、左手で弦を押さえて音を出します。そして、右手で弓を巧みに動かし様々なリズムを刻みベースラインをつくったり、重厚な低音で周りを支えていくのが役割です。
今回はコントラバスの右手の話。弓の持ち方とボウイング練習に挑戦!と題して弓の持ち方と基本的なボウイング練習を解説していきます。
コントラバスの弓には2種類のスタイルがあるって本当?
はい、本当です。
コントラバスの弓には
- ドイツ式(ジャーマンスタイル)
- フランス式(フレンチスタイル)
と言われる2つのスタイルがあります。
弓の種類も違い、手のひらを上にして弓を持つ「ドイツ式」と、ヴァイオリンやチェロなどと同じように手の甲を上にして弓を持つ「フランス式」とがあります。
日本ではドイツ式(ジャーマンスタイル)が主流となっており、ここでもドイツ式の弓を使った持ち方を解説しています。※最近ではフランス式の弓を使用する奏者も増えてきました。
弓の持ち方を解説
弓には2種類のスタイルがあるということがわかったところで、弓を持ってみましょう。
- まず、右手でOKのサインを作ります。

- OKのサインが作れたら、その中に弓を入れていきます。弓のフロッシュと呼ばれる部分が手のひらに触れます。

- 人差し指、親指、そして小指の3点で弓を支えます。
- このまま腕をぶら~んと脱力してみると、3本の指に弓が引っかかっている感覚がつかめると思います。
- そして、あとの2本の指は丸く添えるだけ。薬指はフロッシュを握らないようにしましょう。

これで弓は持てましたか?
※楽器を構えている人は、弓を持ってぶら~んと脱力させた右手を弦の上にセッティングしてみましょう。弓と弦は直角に、セッティングする場所は指板の切れ目より少し下が良いでしょう。
教則本を見ると、この説明とは少し違うことが書かれていたりすることもありますが、ここで紹介している持ち方は数ある中の一つだと考えてください。ドイツ式の弓の持ち方でも国や地域によって様々です。教則本に書かれている持ち方を研究したり、演奏している映像を見て研究してみると良いでしょう。
音を出してみよう
弓の持ち方を覚えたところで、さっそく音を出してみましょう。
まずは弓を弦と直角に、指板の切れ目の少し下にセッティングして弓を左右に動かしてみてください。
いかがですか?弦が振動し、ブーンという音が出ていると思います。
音を出す時には右手をリラックス、力を入れて弓を弦に押し付けないようにしましょう。
ボウイング練習で大切なこと
- 弓をたくさん使ってみよう。まずは元気良く、弓をたくさん使って弾いてみましょう。弦をたくさん振動させるイメージで。
- 弦を横に振動させことが大切です。弓が弦に対して直角になるように弾いてみよう。もし、練習場所に鏡や窓があれば楽器を弾いている自分の姿を確認しながら練習するとよし。
- 弓が上下に滑らないように注意しよう。同じ場所を弾くようにすることが大切です。弾いている時の目線を弓と弦の接点に当ててみましょう。
教則本のボウイング練習はとても重要
今は、コントラバスの教則本がたくさん発売されています。どの本にも必ずといっていいほどボウイング練習が書かれています。楽器を弾く時、まずはじめにボウイング練習をするよう心がけていきましょう。先ほど「弓をたくさん使って元気良く弾いてみましょう」と言いましたが、音価によって弓の量を使い分けることも大切です。
弓をたくさん使えるようになったら
- 全音符は全弓(弓を全部使って)
- 二分音符は半弓(弓元から真ん中、真ん中から弓先)
- 四分音符は1/4(弓元から1/4の量で)
弾いてみましょう。
まとめ
ボウイング練習は、メトロノームを使って取り組みましょう。テンポは60を基準に様々なテンポで練習しましょう。この時に大切なことは「メトロノームに合わせる」のではなく「メトロノームと合わせる」ことです。まずはメトロノームを鳴らしてテンポを感じる、自分の中でテンポを感じられたと思ったら、イチ、ニ、サン、シとカウントをとって音を出してみましょう。