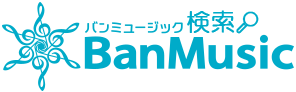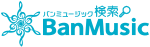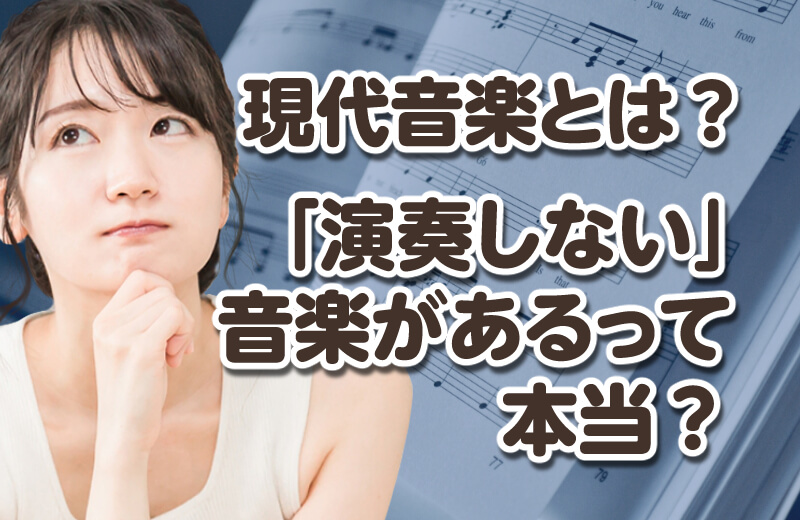
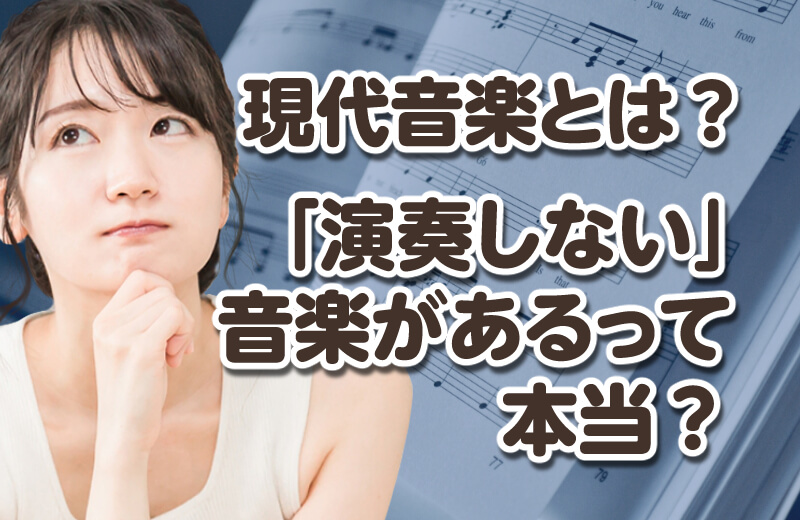
現代音楽とは?「演奏しない」音楽があるって本当?
クラシックが進化した一つの形である「現代音楽」というと、クラシックにもまして難しそう、ついていけないというイメージを持つ人もいるかもしれません。あるいは、イメージすらわかないという人も多いでしょう。今回は、そんな難解な現代音楽の世界について、どのようなものがあるのか、さわりだけご紹介いたします。キーワードだけでも知っておきたいですね。
ジョン・ケージ「4分33秒」

現代音楽といえばジョン・ケージの「4分33秒」が有名です。どのような曲かというと、4分33秒間演奏しない曲です。この曲では、指揮者も演奏者もいて、演奏者は楽器を構えますが、演奏はしません。無音です。これはいったい曲と呼べるのかという議論が巻き起こったのも無理はありません。それでも、この「曲」は評価されているのです。複雑化しすぎた現代音楽に一石を投じたとして、最も単純な音楽を提示したという「価値」が認められています。
ジョン・ケージはほかにも、コイン投げで音楽の進行を決めるなど、偶然性や不確定性を音楽の中に持ち込んだユニークな実験音楽家として知られています。音楽家としてだけでなく、詩人であり、思想家であり、多角的に活躍した人でした。
アルノルト・シェーンベルクと無調音楽

調性のない音楽のことを「無調音楽」といい、これが現代音楽のキーワードの一つとなっています。
調性とは
楽曲がある主音・主和音に基づいて成り立っている場合、その音組織・秩序。(デジタル大辞泉 より)
主音とは、音階の最初の音のことで、ハ長調であればドのことを指します。ハ長調の主和音は、コードでいうとC(ドミソ)です。音組織とは、ハ長調でいえば音階であるドレミファソラシ+ド#レ#ファ#ソ#ラ#のことを指します。秩序がある音楽は、美しいと感じる人が多いでしょう。
調性を放棄し、秩序のない無調音楽を発表した一人として有名なのが、オーストリアの作曲家アルノルト・シェーンベルクです。作品発表当初、これまでずっと調性のある音楽ばかり聴いていた聴衆は、無調の音楽を初めて聞いたときに混乱に陥ったそうです。無調音楽は不協和音ばかりが使われて聞くのも不快であり、難しいというイメージが多いようです。
次のページでは、電子音楽やミニマル・ミュージックなどについて紹介します。