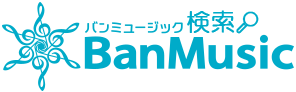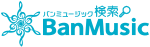音をフワッと響かせる! 魔法のようなフルート練習法5
演奏するときはキレイな音を出したいですよね。では、キレイな音というのは、どういう音でしょうか? 芯のある音。大きな音。音程の良い音。いろいろ理想はあるでしょうし、人によって好みも違います。
でも、だいたい共通するのは、「響きのある音」。モソモソモゴモゴした音を美しいという人は、あまりいません。この「響きのある音」を出すための、簡単ワンステップを紹介します!
過去の記事はこちら↓↓
響きのある音とは?

狭いところでの練習でも広いところでの発表会でも、吹いて息を止めた途端にブツッ……と切れる音。もし、フワッと余韻が残るなら、とても気持ちよく演奏できますよね。
余韻が残ると、響きの中でブレスを取る(息を吸う)こともできますので、フレーズも途切れません。
手首を潜り込ませる!
では、実際にやってみましょう。フルートを構えて、左手の手首を、いつもよりもフルートの下へ押し込みます。これだけです。
手首と手の甲とが90度くらいになります。向きは違いますが、ちょうど、手を肩の辺りまで上げて手のひらを上に向け、その上にトレイを置いて、コップを運ぶような角度です。
手首の柔軟性が無い人には少し辛い状態ですので、身体と相談しながら、なるべく潜り込ませてみてください。
これで音を出すと、音がいつもより軽く、でも芯があって、遠くへ飛んでいくように感じられます。響きのある音への第一歩です。
なぜ効果があるのか?

手首をフルートの下へ潜り込ませることによって、フルートを握っている力が減ります。左手の人差し指の付け根にフルートを乗せるようになるからです。
そもそも、響かせたいなら、なるべくフルートを握らないことが大事です。想像してみてください、金属のパイプを手に持って、ばちなどで叩く様子を。手のひらでぎゅっと握ってパイプを持つより、指先でつまんで持ったほうが、響くと思いませんか。これと同じことです。
また、この角度でフルートを乗せるように持つと、左腕の筋肉が少し緩みます。「高音をキレイに! 魔法のフルート練習法3」でも書きましたが、演奏には脱力が大事。身体の筋肉や神経は繋がっていますので、どこかに余分な力が入ると、別の場所でも不具合を起こします。腕に力が入ることで肩に力が入り、肩に力が入ることで肺の周りや首を固く締めてしまい、息が吸いにくい、力を入れて吹いてしまう、などなど。
いろんな音で試してみましょう

ひとつだけ注意があります。手首を潜り込ませることで、親指の長さが余ってしまうかもしれません。でも大丈夫です、親指のキーは、親指の先で押さえる必要はありません。ある程度自然に曲げる以外は意図的に曲げないで、指の腹(やや側面)で押してOKです。人差し指の付け根あたりでフルートを支えているので、親指にフルートの重みが掛かることはありませんから、自由に動くはずです。
苦手な音や得意な音、いろんな音で、この構え方を試してみてください。思わぬ響き方をする音が、中にはあると思います。そんな時は、何が違うのか、どんなふうに構えたのか、親指はどれくらい曲げてみたのか、と、注意深く観察しておきましょう。指の曲げ方ひとつで、また、置く場所が1センチ違うだけで響きが変わることもよくあります。
音が響くようになると演奏が楽しくなりますよ!