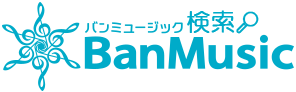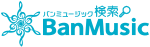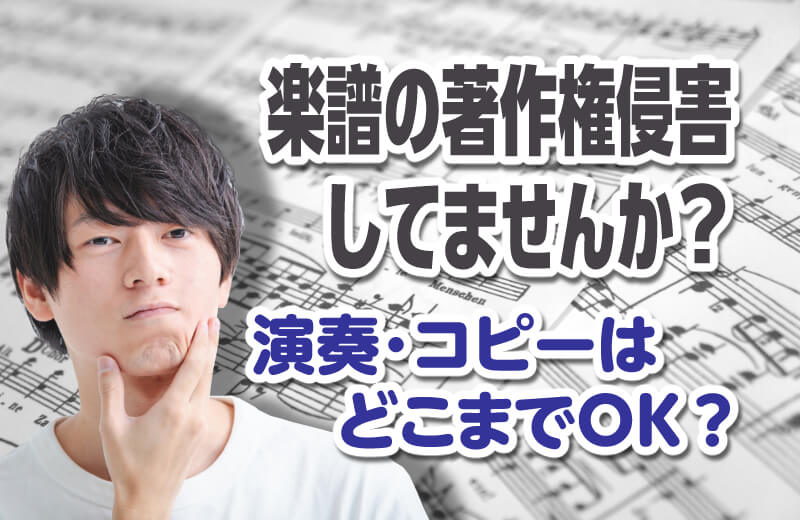
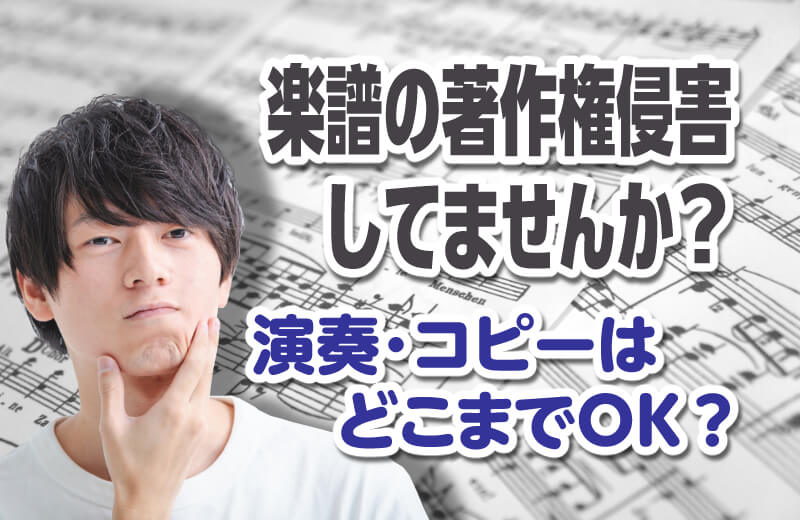
楽譜の著作権侵害してませんか?演奏・コピーはどこまでOK?
学校の授業で使用する楽譜を、著作権者に無断で人数分コピーして生徒に配布することは、著作権の侵害になる可能性があるというニュースを聞いて衝撃が走った人も多いかもしれません。教育目的とはいえ、出版社の利益を損なう形で楽譜を無断使用すると著作権の侵害になります。これは、楽団や合唱団でも当てはまることです。アマチュアのにわかバンドだから…などと言い訳をして、楽譜を人数分コピーして勝手に使っていませんか?プロアマ関係なく、著作権は守らなくてはなりません。今回は、楽譜で犯しがちな著作権の侵害について解説していきます。
楽譜を使って自由に演奏してよい場合
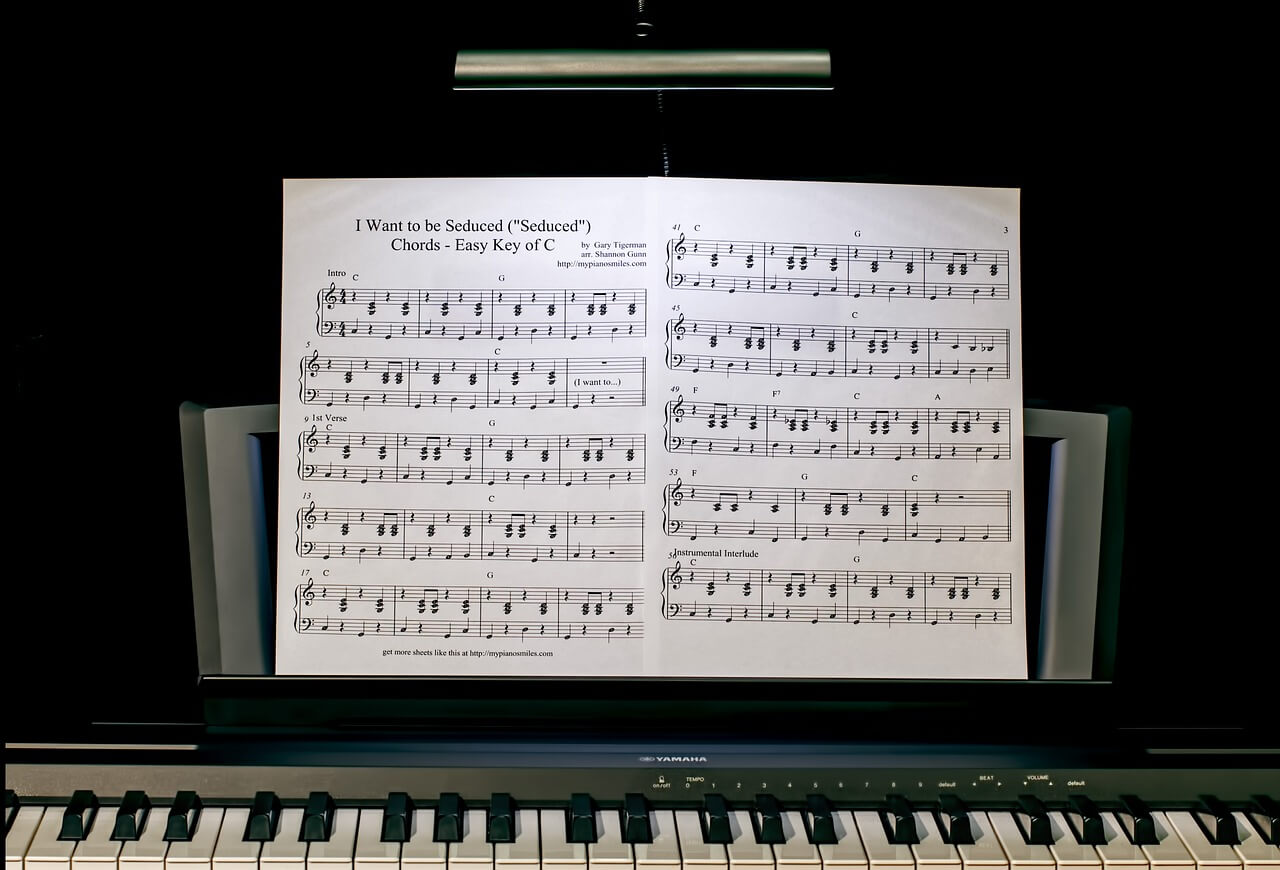
文化庁のHPに、著作権が自由に使えるケースが載っています。例えば、次のような場合は自由に楽譜が使えるということです。
[1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
整理すると、①営利目的ではない②入場料などを観客からとらない③出演者に報酬を払わないの3つが挙げられます。ただ、演奏はしてよいと書いてありますが、楽譜を自由にコピーしてよいとは書いていないので、注意が必要です。
では、出演者に報酬を払わないチャリティコンサートはどうでしょうか?こちらは一部の例外を除き、原則、楽譜の無断使用はできません。募金が入場料に該当してしまうからです。
楽譜のコピーができる場合

例えば、自分で楽譜を購入して、自分で書き込みをして使うなどするために楽譜をコピーすることは可能です。これを私的利用といいます。
また、作曲者の死後70年が経ち、著作権が消滅してパブリック・ドメイン(公共の財産)になるケースがあります。「外国の著作物に関する戦時加算」という例外はありますが、著作権が消滅した楽譜はコピーすることができます。ただし、市販の楽譜の場合は出版社に相談しましょう。
そして、パブリック・ドメインの楽譜ダウンロードサイトというのも存在します。IMSLPなどが有名です。ただし、サイトによっては無断コピーできない曲のコピーが混じってしまっている可能性もあるということも頭に入れておいてください。楽譜の出所は信頼できるところであるかしっかり確認することが、法律違反を防ぐポイントです。
まとめ
基本的に、楽譜をコピーして配布するときは著作権者の許可が必要だと考えた方がいいでしょう。合唱団で人数分の楽譜が必要だからと、一人分だけ楽譜を購入して、二十人分コピーしたら、違法になります。「本当はいけないんだけど」などと確信犯的にやっている人もいるようですが、違法ですので今すぐやめましょう。