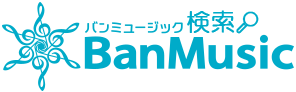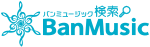フルートの音を大きくするための3ステップ!
フルートを練習している人の多くが悩んでいること……「音が小さい」!
フルートは大きな音が鳴る楽器ではありませんが、それでもフルート協奏曲のように、オーケストラが伴奏をしているのに重ねてソリストが吹いても、ソリストの音はちゃんと聴こえる程度には鳴ります。
大きな音の出せる奏者は、たくさん息を入れたり強く吹いているわけではありません。響かせて吹いています。でも、フルートを練習している私達は、息の量や強さが必要な分にまで届いていないことが多く、響かせる土台が作れていません。
今回は、その土台作りにチャレンジしていきましょう。
響かせる土台を作ろう! 3つの問題を解決!
1.喉の問題

熱いスープを「ふう、ふう」と冷ますように吹くと、口の形はちょうど良いのですが、息を出すポイントが違ってきます。喉を使って吹いてしまっているのです。
大きな音を出すには、深呼吸のように、おなかからしっかりと息を出す必要があります。
低い声で「オー」と言ってみてください。次に、同じ息の出し方で、ヒソヒソ声で「オー」と言ってみてください。そして喉の力をできるだけ抜いてみましょう。このヒソヒソ声の「オー」の出し方だと、喉に力を入れて吹くよりも、音が大きく出ます。
「アー」と発音して、口の形だけを「オー」にするのも良いです。
喉とおなかの感覚を掴んでください。
2.唇の問題

少しおなかが使えたところで、せっかくのたっぷりした息を無駄にしないように、唇の形も考えてみましょう。
大きな音が出ない人の共通点は、空気を出す穴(アパチュア)が小さすぎるということ。それから、この穴が非常に薄いです。「口を横に引っ張って吹く」という教え方が広まりすぎて、多くの人は横に引っ張りすぎになっています。
熱いスープを冷ますような口をしてみてください。かなり縦に開いていると思います。その時、下唇を指で触ってみると、柔らかいと思います。その口で、吹いてみましょう。
※ フルートを口に当てれば、唇はどうしても自然に横に引っ張られますので、自分では横に引っ張らないようにします。
それから、口の中も縦に空けてください。発声練習するような感じで、上の奥歯と下の奥歯の間隔を常に広くキープします。ここが狭いと喉が締まりやすくなり、音が響きません。
3.唄口の問題
さて、三つ目の問題点です。フルートの唄口を、塞ぎ過ぎていないかどうか、チェックしましょう。
ここを塞ぎ過ぎていると、当然ですが太い息が入っていきません。唄口は半分以上あけておきます。
唄口を大きくあけておくことで、倍音が豊かになりますので、よく響く土台となります。
納得いく音が出るまで練習を!
以上の3つの点に気を付けて吹けば、音は大きくなります。ただし、練習しはじめは、荒っぽい、スカスカした音だろうと思います。根気よくロングトーンを続けていれば、だんだんと唇の周りの筋肉が使えるようになってきて、音も良くなってきますよ。諦めないで頑張ってみましょう!