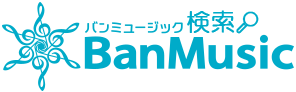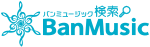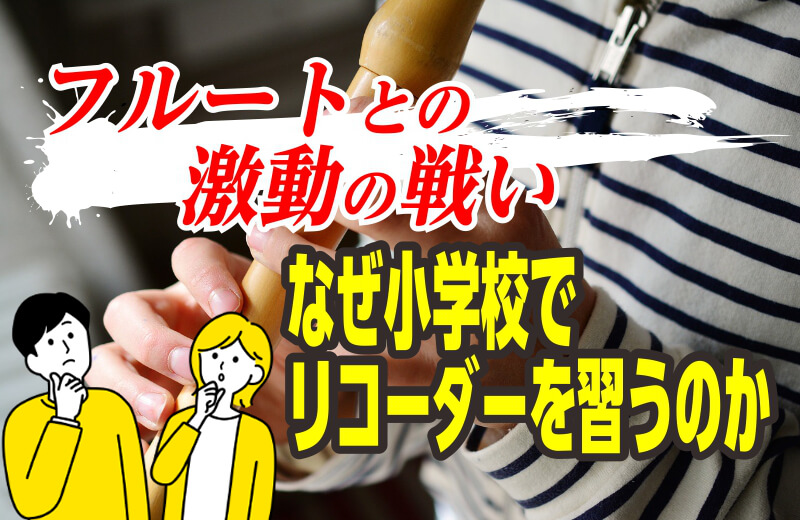
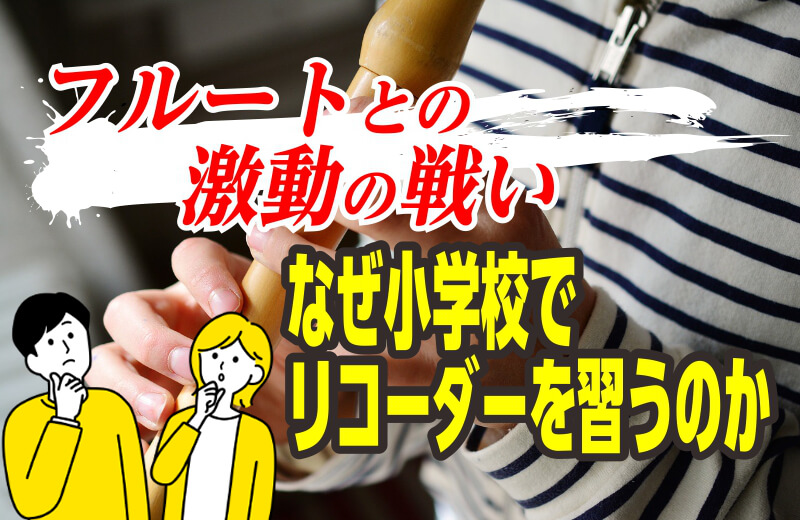
小学校でなぜリコーダーを習うのか【フルートとの激動の戦い】
今回は「リコーダーについて」解説していきます。
私たちは小学校の頃、ランドセルからハミ出しながらリコーダーを持ち歩いていましたよね。
さらに中学校になると一回り大きなリコーダーも手にしていた記憶があります。
では、なぜ小学校や中学校で習う楽器はリコーダーだったのでしょうか。
なぜリコーダーでなければならなかったのでしょうか。
素朴な疑問を解説していきます。
最後にリコーダーの種類についても紹介しますので参考にしてみてください。
では早速見ていきましょう。
リコーダーとは

リコーダーとは、息を吹き込むだけで音が鳴る縦笛です。
かなり安価で簡単に扱うことができるので初心者の方でも上達しやすく、すぐに音楽を楽しむことができるでしょう。
楽器の種類では木管楽器に分類され、他の楽器と比べると指で穴を押さえるだけの簡単な構造になっています。
現代はプラスチック製が多いのですが、材質の硬さなどには指定はなく木材でも作られています。
リコーダーが置かれている楽器屋さんもありますので、購入を検討している方は、それぞれのリコーダーを試奏させてもらうことをおすすめします。
フルートとの関係性

リコーダーはフルートと呼ばれている時期がありました。
現代の「フルート」という名称は「横笛の木管楽器」という意味づけが主流で、リコーダーとも吹き方が異なります。
ではなぜリコーダーはフルートと呼ばれていたのでしょうか。
リコーダーの起源を遡ってみましょう。
リコーダーは中世ヨーロッパの、ルネサンス時代(15〜16世紀)に現在の形が誕生し、バロック時代(17〜18世紀半ば)には多くの方がリコーダーの存在を知り、演奏に使われるようになりました。
その当時は「フルート=笛全般」を意味する語源だったそうで、つまりリコーダーもフルートと呼ばれていたということです。
しかし突如、笛界にライバルが現れました。それは現在のフルートの形をした横笛です。
その横笛が誕生してからは、「フルート=笛全般」ではなく「フルート=横吹きの笛」に改良されたそうです。
フルートはリコーダーに比べると音量や音色も優っており、次第にリコーダーの人気は落ちていきました。
ですがその後、20世紀になり、忘れ去られていたリコーダーに光が差します。
それは古い楽器を研究している方が増えたおかげで、優秀なリコーダー奏者の登場や、リコーダーを教材として使う機会が増えたりと、再びリコーダーは人気になったのでした。
→次のページでは
「小学校でリコーダーを習う理由」について解説していきます。